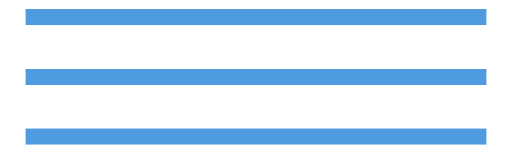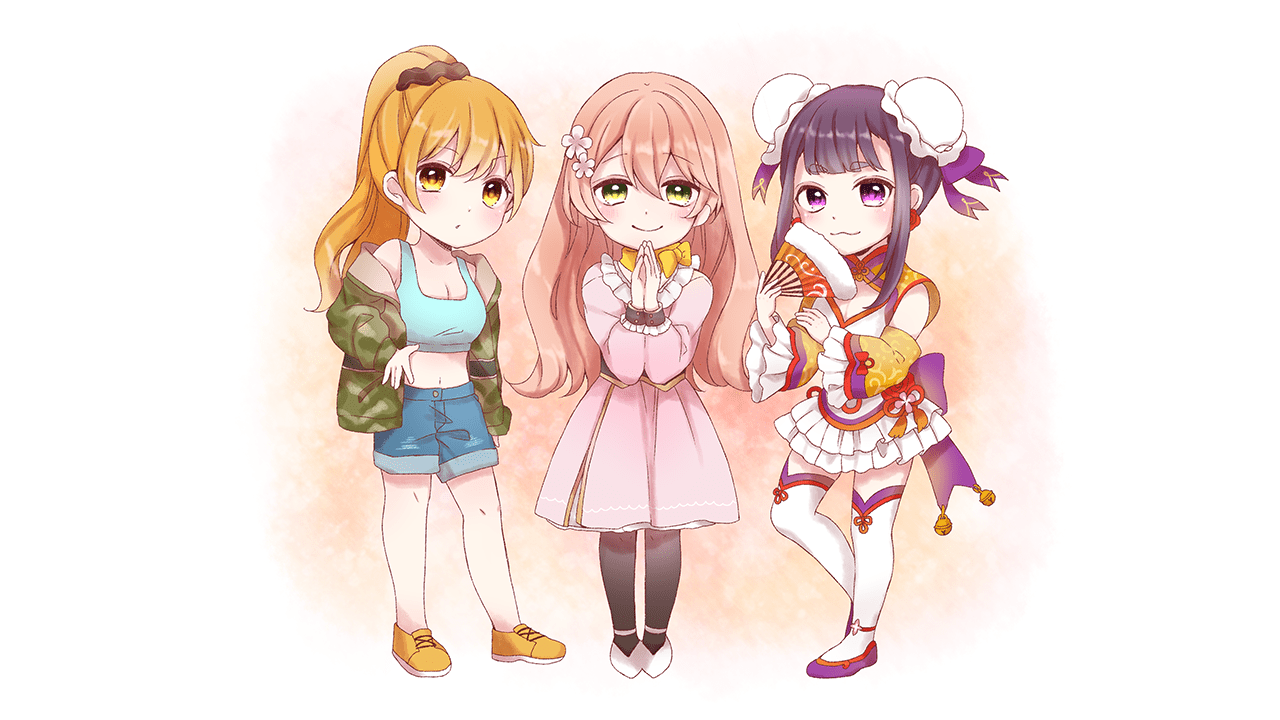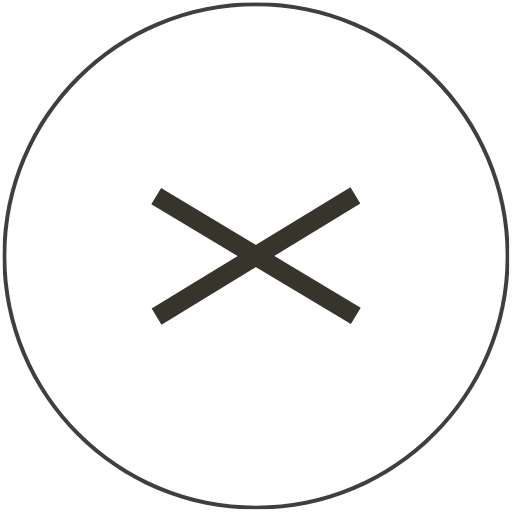夜。誰もいない屋内練習場の一角。
機械に電源を入れる人影があった。
ひとしきり、踊って……。
そして人影は、がくりとその頭を垂れた。
* * *
「あはは、お待たせ~」
あたしが頭をかきながら声を掛けると、1人は声をやや荒げ、もう1人は仕方ないという表情を浮かべた。
ここは芸術芸能学院前駅。そして待っていた2人はあたしの友達のAmeliaちゃんとSophiaちゃんだ。
「あはは、じゃないって……逆の電車乗るとかありえる? もう5月になるっていうのに」
「それがありえるのがRin。Ameliaはそろそろ適応した方がいい」
「SophiaはRinに甘すぎなんだよ」
「Rin イズ マイフレンド」
「なんでいきなり片言なの」
「……あのー、そろそろ行かないと学校に遅刻しちゃうよ?」
「誰が原因じゃい!」
すっかり花も落ち、緑葉樹へと変化を遂げた桜並木を3人で歩く。
1ヶ月近く前に初めてここを通った時は不安でいっぱいだったけど、今はこうして友達と一緒にいられてるし、授業もなんとかついていけているしで、楽しい毎日を過ごせている。
「そう言えば昨日のBIN観た?」
「もちろん」
毎週日曜日の夜に放送されている、アイドル系報道番組のベスト・アイドル・ニュース、通称BINは私たちの大切な情報源の1つだ。
「アイドルユニット・New days tomorrowの野外コンサートで発生した大規模Creaty」
「そうそれ、土砂降りの雨がそこだけ止んだって話」
「うん、あの映像すごかったよね、雲の真ん中にぽっかり穴が空いててさ」
「あれはすごい」
Creatyというのは、あたしたちが目指しているアイドルや、そのアイドルを応援しているみんなが、自分の中に溜め込むことのできる特別なエネルギー。
その力を、あるアイドルとそのファンが使って奇跡を起こしたと、週末のニュースで報道されていたのだ。
きっとみんな、大いにライブを楽しんだに違いない。
「そうそう、超~かっこいい」
こくりと頷くSophiaちゃん。
「ああいうアイドルになれたら、いいな」
「そうだね」
あたしたちはそんなアイドルを目指して、目の前に見えてきた芸術芸能学院に通い、お互い切磋琢磨している。
まだまだ学び始めたばかりだけど、いつか、たくさんの人の前で歌ったり踊ったりして、そしてみんなに幸せな気持ちになってもらえるんだろうか。
考えるだけで、ちょっとドキドキする。
* * *
「はわわっ!」
ドターンッ!!
あたしは思いっきりもんどりを打ち、お尻を機械に打ち付けてしまった。
「いてて……」
その日の午後、あたしたちは室内練習場でダンスの授業を受けていた。
ここにはジムマシンや色んな鍛錬ができる機械が並んでいて、その中にはゲームセンターにある音ゲーみたいなダンス練習マシンもある。操作方法は簡単で、床にある9つの踏み板を、画面に流れてくる譜面表示に合わせて踏む、というもの。また、同時に上半身の状態もボディスキャンして、ダンスに関する様々な要素の採点したり、課題を見つけたりをコンピュータが行ってくれるんだって。
早い話が、ゲームをやって、体幹やリズム感、アピールの基本なんかを学べる機械ってこと。
で、あたしはおっかなびっくり、ダンス、というよりは操作をしていたんだけど、やっぱり難しくて混乱してしまい、最後の最後で思い切り尻餅をついてしまったのだった。
「大丈夫!?」
すぐ駆け寄ってきたAmeちゃんとSophiaちゃんに支えられて、マシンから降りる。
「……32.5点かあ」
画面には総合得点が表示されていた。それはきっと、クラスで、というか学年で下から数えた方が早いレベル。なんだか、みんなとの差を数字で明確に表現されているようなものだった。
「Rin……」
ダンス担当の先生も機械から排出されたプリントを持ってきてくれる。
……見たくないなあ。
「ゴールデンウィーク明けの中間試験でもこの機械を使うんだが……。まあ、頑張れ」
体も痛いし、心もつらい。心配してくれてるんだろうけど、2人の目線もちょっとつらい。
最近、授業についていけてると思ってたから、ちょっと調子に乗ってたのかな……。
久しぶりに、参った。
* * *
放課後、あたしたちのクラスの全員が体育館に呼び出された。
いや、あたしたちのクラスだけではない。恐らく上級生と思われる人たちも呼び出されていた。
「人がいっぱいだね、何の用事なのかな……」
「……え、知らないで来たの?」
Sophiaが目を丸くして言う。
「うん……、Ameちゃんは知ってる?」
「さ、さすがに知ってる。ってか、昨日先生が言ってたじゃん」
「あう……、またあたしだけ……」
「まあまあ、いつも通りでよろしい」
あたしの肩をぽんぽんと叩いて慰めようとするAmeちゃん。
「きっと、すぐにわかるから大丈夫」
周囲のみんなが楽しそうにざわざわとおしゃべりを続ける中、チャイムが鳴り、Marguerite先生ともう1人の上級生担当の先生が現れ、あたしたちの前に進み出た。
「はい、静かにして。全員その場に着席」
いつものキリッとした先生の発言に従い、全員腰を下ろす。
「それでは、これから毎年恒例のチューターの顔合わせを行う」
チューター? なんだか聞き覚えのある言葉だけど……。
「皆も知っての通り、当学院では2年生が1年生の面倒を1対1で見る、通称チューター制度というものがある。ここに集まっている1年3組と2年3組が対となる形だ」
先生たちが矢継ぎ早に説明を続ける。
「1年生は学院内外の様々なことで悩むことがあるだろう。また、交友関係を広げたいなど、解決したい課題が現れるかもしれない。その際は是非チューターを頼りにしてほしい」
「そして2年生諸君、君たちはチューター制度を通して、将来、悩む人々の力になれるよう、その能力や知識を磨くための練習だと思って取り組んでほしい」
「な、なるほど……」
ぼうっと説明を聞いていたためか、思わず声を出してしまうあたし。
「さて、それではこれからペアを発表する。学院で多角的な視点から判断し選んでいるが、ペアに問題が出た場合は、随時我々教員に連絡してほしい。調整を行う」
Marguerite先生は手に持っていた名簿にあった、名前を読み上げ始めた。
1人ずつ、まず1年生の名前が呼ばれ、続いて2年生のチューターの名前が呼ばれる。名前を呼ばれた者同士は握手をしたり、互いに一礼をしたりして、その後体育館の脇の方に移動しては、自己紹介をしているようだった。
「続いては、Rin」
「は、はいっ」
名前を呼ばれて、あたしは立ち上がる。
「Rinのチューターは、……Youran」
先生が名前を言った瞬間、おー、と声が上がる。もしかしたらYouranさんは有名人なのかもしれない……などと思っていると、スタイルのとてもいい女性がスラっと立ち上がり、こちらに歩み寄ってきた。
黒髪が美しく、それらは頭の二箇所で留められている。いわゆるツインのお団子ヘアにした女性だった。
「はじめまして、私がYouran。よろしくね」
「あ、はい、Rinです。よろしくお願いします」
ペコリとあたしが頭を下げると、彼女もうんうんと頷いていた。
他のペア同様、あたしたちも体育館の隅で自己紹介をすることにした。
「へえ、Rinちゃんはアイドル志望なんだね」
Youranさんは話してみるとすごく気さくで、とっても明るい性格の人のように感じられた。それに身のこなしもとってもきれいで、ただ歩いているだけなのに、素敵だなあって思えた。
「Youranさんは、何を目指しているんですか?」
「そうだなあ……うーん、よくわかんないや」
「え?」
「みんなが面白がってくれたら、何でもいいかな、うふふ」
人懐っこい笑顔が本当に似合う人だ。やっぱりクラスでもきっと人気があるんだろう。
「なるほど、Youranさんはエンターテイナーってやつなんですね。あたしもおんなじです。みんなを楽しませられるのが一番だなあって思います」
あたしがそう言うと、Youranさんは目を細めた。
「ふふ。まあ、それが難しいんだけどね。一緒にがんばろうね」
「はい!」
あ~、なんか。いい人そうでほっとした。
* * *
「RinのチューターのYouranさんって人さ、2年次でもトップクラスの実力の人らしいよ」
「名前を呼ばれたとき、周りから声がしてた」
「そうなんだ、やっぱりなあ」
次の日の昼休み。中庭でいつものようにAmelia、Sophiaの2人と集まって、ご飯を食べていた。
今日の話題はもちろんチューターについてだ。
「やっぱりって、どういうこと」
「なんかさ~、いるだけで存在感があるっていうか。親しみはあるんだけど、圧倒されちゃう気持ちもある」
「あ~、わかりみがすごい」
びっくりするくらい大きなカレーパンを頬張るAmeliaは、今度は自分のことについて話し始めた。
「私のチューターは、Camilleさん。話聞いたことない?」
「ある。2年次でも有名なアイドル候補生の1人」
「さすがSophiaちゃん、何でも知ってるね。略してさすソフィ」
「何それ」
「まんざらでもないみたいな顔すんな。……でも、おっとりしてっていうか、ふわふわした人で面白かったなあ、Camilleさん」
「Ameliaです、よろしくおねがいします」
「あら~、可愛い! よろしくね」
「Camilleさんですよね、聞いたことがあります」
「え~? なんて?」
「すごく綺麗で、優しくて、アイドル目指してる人だって」
「え~? なんか恥ずかしいな~、うふふ」
ひとしきりCamilleさんの印象について語られると、今度はSophiaちゃんが話し始めた。
「私はEmmaさんって人で、なんかカッコいい印象。サバサバしてて、私とはタイプが違う感じ」
「やあ、こんにちは。キミがSophiaさん?」
「はい、よろしくお願いします」
「へえ、アイドルと歌手のダブルか。優秀なんだね」
「そんなことは、ないです、けど」
「そう? もっと自信持ったらいいのに。これからよろしくね」
その後も2人は色々学院のことについて情報交換をしたらしい。
「Sophiaがきちんと会話できてるってことは、いい人なんだろうな」
「……どういう意味」
「Sophiaは敵意を感じたらすぐ敵意で返すだろ?」
「でも逆にさ、Sophiaちゃんがいい人って思ったら、いい人ってことだもんね」
「……私は検知器か」
2人もそれぞれのチューターに対し、自分とは違うタイプながらも、好印象を覚えているようだった。よかったよかった。
きっとあたしたちの性格をちゃんと見抜いて、チューターを選んでいるんだろうなあ。さすが芸能学院だ。
でもあたしが、そんなトップの人とペアだなんて、いいのかな。
* * *
「お姉ちゃん、お風呂!」
ドアの向こうからMimiのやかましい声が聞こえる。
「待って、あと少しで終わるから……」
ちょうどあたしは学内のSNSを使って、メッセージを打っているところだった。
今日のダンスの授業、これからどうしたらいいかずーっと考えていたんだけど、結局答えが出せなくて、ヒントをもらいたいと思ったんだ。
「もう、お姉ちゃん!」
ドアをバタンと開けて私の部屋に乱入してくる妹。
「だー! もう、入ってこないでよ」
「お風呂!」
「わかったってば……」
あたしはそっと送信ボタンを押した。
「メッセージくれるかなぁ……Youranさん」
* * *
その次の日。学院で、1つの机を囲んで昼食を摂る3人がいた。
1人はYouran、あとの2人はAmeliaのチューターであるCamilleと、SophiaのチューターであるEmmaだ。
元々旧知であり、今はクラスメイトでもある彼女たちは、担当する下級生が友人同士ということもあってか、さらにこうして親交を深めていた。
「なかなか面白いよね、チューター制度ってのも」
「そうですね。去年の自分もあんな感じだったんだろうなあと思うと、ちょっと恥ずかしいですけど」
「……Youran、何黙ってるのさ」
CamilleとEmmaが談笑を続ける中、Youranは何か考え事をしているように見えた。
「……ん? いや、別に……」
「別にって顔してないぞ。その、あの子……」
「Rinちゃんだよ」
「ああ、そうそう、そのRinって子。どうなの?」
「あの子もなかなか可愛いじゃない?」
Emmaの言葉にCamilleが笑って答えると、Youranはため息を一つついて続けた。
「まあ、ちょっとあってさ。それに自分は自分でやることやらないといけないし、色々ね」
そう言うと、ややキリッとした表情を浮かべるYouran。
「確かにまあ、ゴールデンウィークが終わったら中間試験だけどさあ」
「……ん? どうしたの、Youran」
今度はうっすらと笑みを浮かべるYouran。
「……そうか、中間試験か」
* * *
「えええええ!」
「あたしたちと先輩たちで3対3のダンスバトル!?」
「そ、ダンスバト~ル!」
満面の笑顔で言う、Youran。
そして、大口を開けたまま凍り付く、あたしとAmeliaちゃんとSophiaちゃんの3人。
昨日打ったメッセージが、授業の終わり頃に返ってきたと思ったら、『放課後、ダンス練習マシンの前に3人で集合』って書いてあって……。
来てみたらいきなり、Youranさんは何を言い出しているんだろう。
「マジで言ってますか」
「マジだそうです」
「マジなんだってさ」
Youranの後ろにいるCamilleとEmmaがフォローする。
「単純に、このダンス練習マシンで3人の合計得点が多い方が勝ちってルールだから、そんなに難しくないって。心配しないで」
「あの、あたし、この前これ32点で、クラスでも下の方で……」
あたしがぼそっと言うと、Youranさんは続けた。
「だから~、今の得点のままじゃ中間試験、まずいんでしょ?」
「この機械さ、同好会とかのグループ活動の一環でしか貸し出し禁止なんだよね。だから、対策用にこうやって練習の機会をでっち上げてしまえば使えるってわけ。な? 上級生のみが知ってる裏技さ」
Emmaが得意げに言うと、下級生3人は、おーと声を揃えて感心した。
「な、なるほど、確かに……」
「でもなんで、練習じゃなくて、ダンス『バトル』なんですか」
そのSophiaの質問に一同が凍る。
「えっと~、……うーん、ノリ?」
あれ、今一瞬Youranさんの本性が見えてしまったような……。
「バトルは明日の放課後ね。今日いっぱいはこのマシンを使えるように先生に話しておいてあるから。さあ、レッツエンジョイ、ダンスバト~ル!」
* * *
「じゃ、じゃあ踊ろっか」
あたしたちはすぐに教室に踵を返し、ジャージに着替えてから戻ってきて、ダンスマシンに挑戦しようとした。
が、先輩たちはその場に残っていて、帰る間際にアドバイスをしてくれた。
「えっと、まずは……」
アドバイスその1。
まずはマシンに設定されている曲を色々試して、自分に合う選曲を行うこと。その際、自分が表現しやすいと思える楽曲にすること。
「このボタンを押すと、次々と曲が流れるんだって」
3人で1つずつ楽曲を探していく。
「あ、私これがいいかも」
クラシカルなバレーダンスのような楽曲を見つけるSophiaちゃん。
「私はこっちかな」
聞いてる方が楽しくなるような明るいポップな音楽をチョイスするAmeliaちゃん。
「あたしは……」
とりあえず、オーソドックスなアイドルソングを選んでみた。
アドバイスその2。
いきなり踊るのではなく、譜面をチェックしながら一つひとつのパートを確認して、頭の中で自分の体の動きが想像できるようにすること。
マシンを操作すると、各楽曲の詳細な譜面表示を調べることができた。「なるほど、曲の中でどの音が重要視されているかも調べておかないといけないね、これは……」
その後で、ようやく踊る。
アドバイスその3。
調べて理解し、想像できた姿に、自分を近づけていくこと。
って、言われて、できたら苦労はしないんだけど……。
繰り返し踊っているうちに、SophiaちゃんもAmeliaちゃんも、何か掴んだものがあったようで。
「お、5点くらい上がった!」
「私も」
と喜んでいた。あたしは……。
「……32.6。下がってる!!」
何度も試してみたが、疲れてきた時のカラオケみたいに、どんどん得点は下がっていくばかり。
率直に言って、悔しい。
「ま、まあ、……がんばろう」
「Rin、リラックス」
「う、うん……」
気持ちがブルーになるのと同じように、空の色も一気に暗がってきた。
「そろそろ、切り上げよう」
あたしに疲労の色を感じたのか、思い切ってSophiaちゃんが伝えてくる。
周囲を見渡すと、練習場にはもうすでにあたしたち以外には誰もいなかった。
「Rin、まあそんなすぐ上手くいかないって。バトルがどうなっても取って食われるわけじゃないし、気にしないで」
「うん……」
3人がマシンを丁寧に拭き掃除し、部屋の電源を落として外に出た後。
「……暗っ」
しばらくしてから、室内練習場の奥からスマホが照らす明かりと共に、ふらりと人影が3つ現れた。
「みんな頑張ってたわね」
「若いっていいな~!」
「あのねえ、1歳しか年違わないでしょ」
3人のチューターは思わず見合って笑った。
* * *
部屋から出た1時間22分後。
再び室内練習場に明かりを灯し、マシンに電源を入れた。
あたしは1人、あの後学院にこっそり戻ってきた。
マシンを操作して、再び向かい合う。
あたしは、人より少しでも努力しないと……。
さっき選んだアイドルソングを選び、闇雲に踊ってみる。
でもやっぱり、自分が想像しているように、体がついていかない。何かの表現にたどり着いているとは到底思えない。
得点は31.8点。
画面を見た瞬間、疲れがどっと体に押し寄せるようで、力が抜けてしまった。
やっぱり悔しい……。
「諦めるの?」
いきなり凛とした声が背後からして、背筋に電流が走るようだった。
「あ、す、すみません!」
「あははは、なんで謝ってるの」
後ろを振り向くと見知った姿、Youranさんが立っていた。
「……Youran、さん……」
あたしは彼女のいきなりの登場に、気持ちの緊張が切れたのか、半泣き状態になってしまった。
「う、うえ……」
「おおお、おい……大丈夫か……?」
しばらくYouranさんはあたしの側にいてくれると、立ち上がってこう言った。
「さてと。じゃあ、もう一回踊ってみよっか。これからはマシン無しね」
Youranさんはあたしにそう言って、練習場の端に移動すると、スマホから音楽を流し始める。
「え、えっと……」
「ほら。こっちおいで。体を動かす~動かす~」
Youranさんが再生したのは、高級中華レストランで流れているような、中華風のゆったりとした音楽だった。
それに合わせるように、Youranさんが踊る。
踊るっていうか、舞うっていう言葉の方が近いかもしれない。
至って普通のジャージ姿なのに、まるで一級品の舞踊衣装を纏っているかのような風流な印象を覚える。
うっとりしながらそれを観ていたら、Youranさんが口を開いた。
「こら~。一緒に踊るんだってば」
「あっ、あ、そうでした。すみません、見とれちゃいました」
「あはは、うれしいけどさあ。さ、がんばろ」
Youranさんの横で踊るのは、比較されそうで正直かなり恥ずかしい。けれど、せっかく時間を作ってもらっているんだ。腹を決めて、見よう見まねでやってみることにする。
「うんうん、可愛い可愛い。そうそう、自分が思う通りに体を動かしたらいいんだよ」
そう言いながら、Youranさんは手首を翻し、指先で何かを表現しようとしている。
「あのダンス練習マシンの判定もさ、結局最終的には譜面を覚えないといけないんだけど、総合的なダンス能力の方が優先して加点されるから。とにかく音楽を良く聞いて、感じたままに動いてみることを優先してみて」
「はい」
Youranさんはそう言いながら、音楽のテンションに合わせるように、さらに手足を伸ばして大きく体を使ったり、リズミカルに動き回ったりする。本当、綺麗だ。
「そうだなあ、例えるなら、音楽に身を預ける感じ?」
「音楽に、身を預ける……」
「何か自分の中に浮かんでくるイメージがあれば、それを大事にして」
イメージ? イメージか……。
音に埋もれるように、か。
ふうと息を吐いて、深呼吸する。いつの間にか、目を閉じる。そうすると、なぜだろう。想像があふれてくる気がした。
川、かな。そこに浮かぶ桃があたしかも。波に揺られて、どんぶらこ。どんぶらこ……。
「……ん?」
あたしは川に浮かぶ桃。どこに向かってるんだろう、自分でもわからないけど、遙か遠く、もしかしたら海? を目指して、まっすぐ川を下っていく桃……。
「……へえ」
そのとき。
不意に音が止まった。いや、Youranさんが曲の再生を止めてただけだった。
「……よし、ここまで」
「え、もうですか?」
そう言った瞬間、腰が砕けるように地面にへたれこんでしまった。
いや、あれ? もしかして時間が結構経ってる?
「ほらほら、大丈夫? 全然もうじゃないよ、もう3ループもして、10分以上集中して踊ってたよ。疲れたでしょ?」
「あの、今は大丈夫です。なぜか」
「そっか、よかった。何か見えた?」
「……桃です」
「も、桃!?」
あたしの手を引いて立たせてくれるYouranさんは、目を丸くして驚いていた。
「はい。川を流れる桃です。波の一つ一つが桃に当たって、波にも強い弱いがあって、岸とかにぶつかりながらも、それでも下流に流れていく感じで……」
「ああ、なるほどね」
「例えば、42秒前に聞こえた、どかーんって太鼓の音も、桃に大きな波がぶつかった感じで、その6秒ちょっと前と17秒くらい前かな、シンバルみたいな音が、で、あと……」
「ちょ、ちょ、ちょっと待って、……今なんて?」
「? え、えっと、どかーん?」
「そ、そうじゃなくてさ……」
Youranさんはちょっと面を食らったように見えて、その後プッと吹き出して、最後には、ふうと息を大きく吐き出すと、あたしの肩に手を触れた。
「……ま、いっか。大丈夫、Rinは成長するよ。本当、疲れたでしょ、続きはまた今度」
相変わらず笑顔が可愛いYouranさん。彼女に褒められて、正直少しほっとした。
「あ、はい、ありがとうございます! ……あたし、諦めません」
「うん、よく言った! じゃあ、帰り何か食べて行こうか」
「はい! ……せっかくだから桃がいいです」
「……えええ、桃かあ……」
* * *
翌日、放課後。
「準備はいい?」
「はい!」
全員が準備体操を終えると、いよいよダンスバトルが始まることになった。