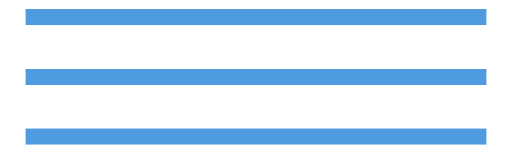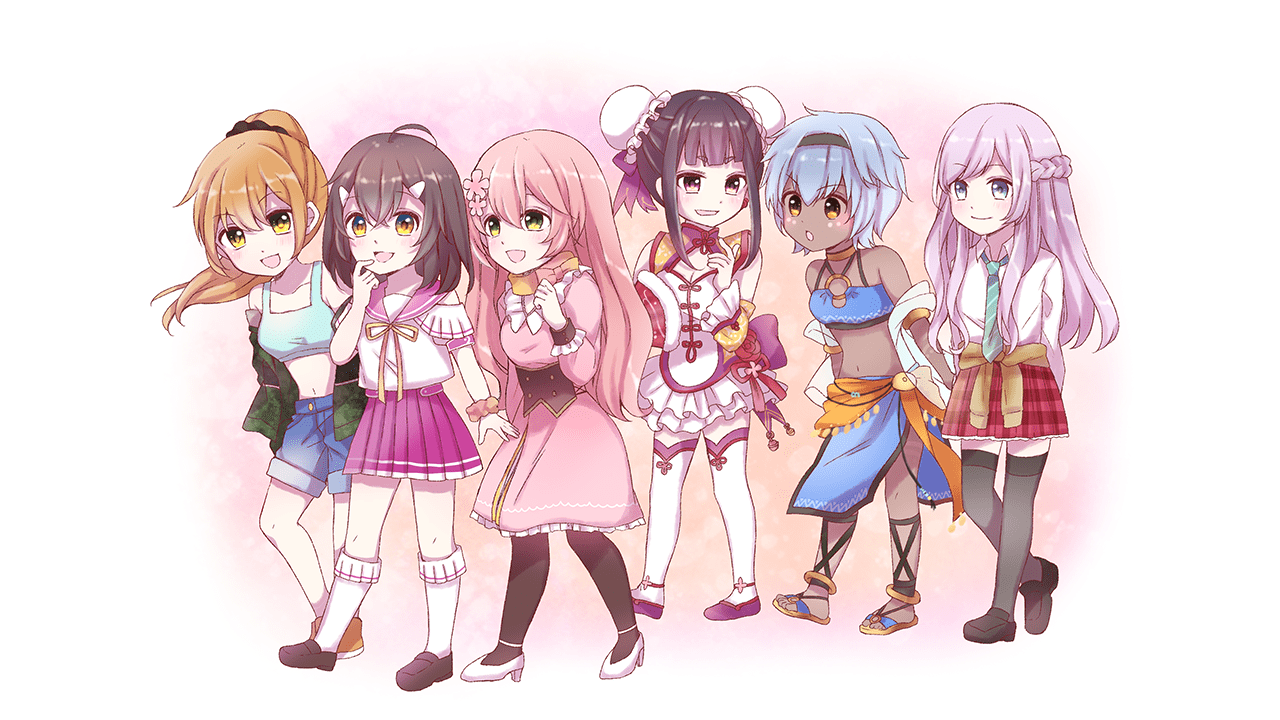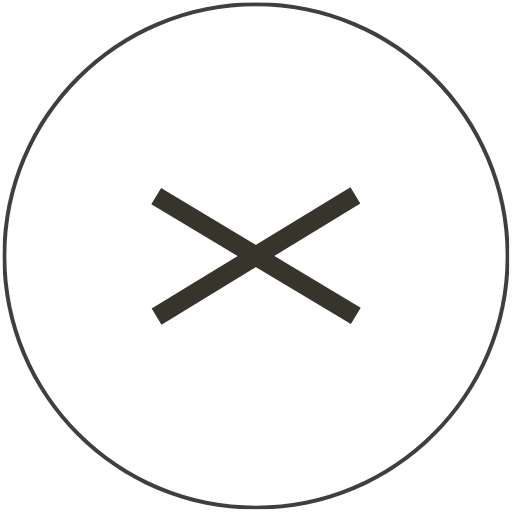「じゃあ、いっちば~ん」
機械の上にぴょんと飛び乗るAmeliaちゃん。こういうときに率先して行動できるのは、本当に羨ましい性格だ。
昨日選んだ通りの選曲をすると、軽快な音楽が流れ始め、画面にマークが表示され始めた。Ameliaちゃんは譜面をきちんと目視しながら、軽やかに宙を舞う。
「あら、素敵ですね」
「やるじゃない」
「ほっ、はっ、ほっ!」
元気いっぱいに体全体を使って踊る彼女。腰つきが見事だなと思えるのは、体幹の良さからだろうか。
「イエイ!」
そんな彼女が踊り終わる頃には、顔にびっしりと汗をかいていた。
画面に大きく得点が表示される。思わず歓声が上がる。
「はえ~、でも68.9点かあ。難しいなあ、こりゃ」
そうは言っても、この得点は1年生の中では恐らく上位にランクされるだろう。息も上がっているようには見えない。この元気いっぱいの体力や、肺活量の強さも彼女の長所の一つだろう。
「よくがんばりましたね」
「すごいすごい」
「えへへ」
先輩たちが褒めてくれると、Ameliaちゃんはまんざらでもないという表情を浮かべた。
「それじゃあ、次はチューター組だから、私が踊りますね」
続いて、Camilleさんがダンスの上に進み出た。
選曲は直球のアイドル元気ソング。
そしてそのダンスも、正統派のアイドル振り付けだ。
「可愛い……」
「これぞアイドルだな……」
初めてのCamilleさんのパフォーマンスに、思わず声がこぼれる。
2年次の中でも天才肌と呼ばれる彼女は、持ち前の表現力であたしたちをも魅了してしまった。
気づくといつの間にかダンスも終わり、採点結果も表示されていた。
「うーん、83.4かあ。なかなか難しいなあ」
いや、これは恐らく学院の中で、2年生で、しかもダンサーではなくアイドル専攻としてはかなりのレベルな方だろう……。やはり上級生はすごいのか、それともCamilleさんが飛び抜けてるのか……。
「次は私」
続くSophiaちゃんの選曲は、昨日選んだクラシックなあの曲。
流れてくる譜面に的確に優雅な表現を合わせ、それにオリジナルの振りも入れながら踊る。
やっぱり、彼女はあたしたちの一歩先を行ってる気がする。
「得点は、64.2!」
「うう……Ameliaに負けた」
「あのねえ、たまには私にもリードさせてよ」
でもAmeちゃんは結構嬉しかったみたいで、軽く飛び跳ねているのがわかった。
「ははは、声楽専攻でダンスまで高得点だったらたまらないさ。私がちゃんとこれから教えてあげる」
「はい、よろしくお願いします」
SophiaちゃんのチューターであるEmmaさんがフォローする。こういうところが、Emmaさんってすごく優しい気がする。
「よし、じゃあ敵討ちと行くか~」
ぶんぶんと腕を振り回しながら、マシンの上に乗るEmmaさん。
「あのねえ、どっちチームなのよEmmaは」
「私? 私は私。そしてSophiaのチューター。That’s All.」
キリッと笑顔を見せて、マシンに向き直るEmmaさん。
彼女は機械を使い慣れているんだろう、テキパキとロック調の楽曲を選ぶと、手足首をくりくりと回して、ストレッチしながら言った。
「このダンスは、Sophiaに捧げよう、なんてね」
そこからのダンスはまさに圧巻。
エネルギッシュな振り付けと、情熱的で感情的な人々を魅了するアクション。
Emmaさんには女の子たちによるファンクラブがあるって噂があるけど、それって本当なんだろうなあと、見ていて思ってしまった。
曲が終わり、汗一つかかず台から降りてくるEmmaさん。振り返って、画面を見つめる。
「得点は……89.2!」
これは、すごいというか、もう刺激的なレベルの得点だ。
さすがダンサー専攻。でも正直、得点に納得感しかないパフォーマンスだった。
「ははは、どうだった?」
Sophiaちゃんは……、やはりいたく感動したようで、こくこくと頭を上下に振っていた。
この数日間で、彼女はEmmaさんのことを随分信頼し始めているように思える。さすがにファンクラブには、入らないよね?
次は……あたしか。
ふうとため息をついた。そして、一歩前に進み出ようとする。しかし、あたしを遮るように目の前に腕が現れた。
「Rinちゃん、ごめん、先やらせて?」
「え」
そう言うが早いか、Youranさんはマシンの上に乗り、慣れた手つきで手早く機械を操作し、曲を選んでしまった。
優雅な音楽が流れてくる。
「この曲は……」
そう、昨日Youranさんと一緒に踊った曲だ。
彼女は両腕を伸ばして構える。思わずあたしは息を呑んでしまった。それほどまでに、Youranさんは真剣な表情に変わっていた。
「あらあら、本気ね」
「ま、お手並み拝見ってね」
そこからのYouranさんは圧巻だった。
それこそあたしに教えてくれたように、頭の先からつま先まで音楽を纏うがごとく、艶やかさを表現しきっていた。
もうあたしたち下級生組は、勉強しようとか、技を盗もうという気にすらなれず、ただ呆けたように見守るしかなかった。
それでも、あたしはがんばって、聞いて、見た。
Youranさんが『音楽に身を預ける』様子を。
曲が終わって、画面に数字が現れた。
「得点は、……92.2!!」
あたしたちから、うわあと大きな歓声が上がる。
やはりぶっちぎりですごい。実力を、まじまじと見せつけられた。
「いやー、本当久しぶりにやったけど、まあこんなもんかな」
「なんだよこいつ、自慢げにさ~」
「あはは、でもまだパーフェクトじゃないし」
「くっそー、腹立つなあ」
YouranさんとEmmaさんが小突きあって、それをCamilleさんが見守っている。本当に余裕の、つまり実力のある人たちにだけ許される光景だった。
最後に残されたのは、あたしだ。
思わず、生唾を飲み込んでしまう。
「Rin。もう私たちは合計得点じゃ勝てない。何も気にしないで」
そう、すでに2つのチームの差は、100点を超えてしまっている。あたしがどんなに頑張っても、抜けることはない。
「そうそう、Rinがやりたいようにやろう、ね」
2人が声をかけてくれる。
そして、Youranさんも。
「Rinちゃん、大丈夫。感じたままに、ね」
「……感じるままに」
Youranさんの瞳に誘導されるように、あたしも恐る恐るマシンに乗る。
ふうと一度、深呼吸。
この選択しか無いと思った。曲がスタートする。
「……え?」
「昨日のアイドルソングじゃない?」
「っていうか……、Youranと同じ曲だ」
そう、選んだのは、あの中華レストランみたいな曲。
譜面を見たことないけど、この曲で、今のあたしにできるだけの表現をしてみよう。
大事なのは、音楽に体を委ねること、身を預けること……。
不意に、何かが見えた気がした。
あたしの中? に、まるで、音楽が金色のヴェールとなって、それを纏うようなイメージが生まれていく。
そのヴェールを弄ぶように、天女のように、ひらひらと浮遊を楽しんで、舞うような感触。
「Rin、きれい」
「うん……」
AmeliaちゃんSophiaちゃんは、あたしのことをじっと見つめているようだ。
「いいね」
「ええ」
「……」
先輩たちも、笑顔でいるっぽい。
あたしが今できる精一杯のダンスは、できた気がするな。
体を静止させた。
曲が、終わった。
あたしはそれと同時に力が抜けて、やっぱり尻餅をついてしまった。
思わず、SophiaちゃんとAmeliaちゃんが駆け寄る。
「あはは、やっぱり無理だった、ごめんね、2人とも」
「ううん、がんばったよ、Rin……!」
「なんでお前が泣きそうなんだよ……」
「だって、だってぇ……ずごいよがったもん!」
「え、ええ……」
ちょっと引き気味のAmeliaちゃんが、半べそになっているSophiaちゃんにハンカチを貸してあげている。
精一杯踊れた。嬉しい。
画面に現れた表示は
「……54.2!」
あたし史上最高得点だった。
「うおっ!」
「やっだよー!」
AmeliaちゃんとSophiaちゃんが抱きついて喜んでくれた。でも一番下。それが今の実力なんだ。
「よかったな、54点なら中間テストでも及第点だよ」
「21点もアップしたんでしょ? 昨日の今日で、どうしてこんなになったのかしらね」
EmmaさんもCamilleさんも喜んでいる。
「あ、あの、それはYouranさんが昨日の夜アドバイスをくれて」
「あれま~、いつの間にYouranは名コーチに」
Youranさんは腰に手を当てて、自慢ありげに冗談ぶる。
「へへ~、すごいでしょ~」
そして、あたしのそばに寄って、また手を差し伸べてくれた。
じっとあたしの目を見て言う。
「Rinちゃん、自信持って。3人とも、これからもがんばろうね」
「……はいっ!」
あたしたちは大きく声をあげた。
* * *
「ねえ、いい? 2人とも」
「ん? どした?」
残って後片付けをしていたCamilleとEmmaに、Youranが声をかけた。
「まだ何か調べてんのか?」
「点数は確かにみんなより低いんだけど……でもよく見て」
Youranがスコア表示の画面を指差す。
「これは……Rinちゃんの成績の詳細表示ね」
「アピールとか重心バランスとか……、身体能力も極端に低いか……、まあこれは仕方な……あ!?」
2人が思わずYouranの方を見ると、彼女は深く頷いた。
「タイミングの項目だけは、補正後値99.99%!? しかも、実際の多くの入力誤差が0.01秒以内、しかも誤差が大きいものについては、身体的能力が劣るからついていけてないだけってコンピュータの判断って……何これ……」
Emmaが目を見開き、信じられないといった表情で画面を見つめている。ダンサーである彼女はこれがいかほどに驚異なことであるか、重々承知しているだろう。
「恐らくCreatyを自己発動してたんでしょうね。私たちには感じられない範囲で」
Camilleも、なるほどと言った表情を浮かべる。
「でも、それだけじゃ、この値は無理よ」
Youranは続ける。
「……この数値はまさに『神の領域』」
CamilleとEmmaの2人は、ほぼ同時にごくりと唾を飲んだ。
「ダンスという一面だけでも、こんな結果になるなんて。ふふ、やっぱり面白い子たちですね」
「マジかよ~! 他にもどんな能力を秘めているんだろうな。やっぱこの学院のやつらは面白いな~!」
Youranはしばらく画面を眺め、そして自分の結果がプリントアウトされた紙に目を落とした。
92.2点。万人が褒め称えるであろう、歴代でもトップクラスの内容。
全てのグラフが満点ラインを指し示し……ただし、1つだけ。
『タイミング』の項目グラフだけ、凹んでいるのが目に入った。
「……あのさ」
Youranが口を開く。
「2人に、提案があるんだけど」
* * *
翌日。あたしたちはこの2日間のダンスの疲労感を全身に抱えながら、桜並木を歩いていた。
「あう、筋肉痛が……」
「足、動かない……」
「2人ともがんばろ、今日は金曜日だから……」
「放課後、遊ぶぞぅ……!」
ひいひい言いながら学校へ歩を進めていると、その3人の目の前に見知った人影が現れた。
「やあ、3人とも。元気、じゃないよね、あはは」
それはEmmaさんだった。
「ど、どうしたんですか?」
「どうしたって、朝登校してれば一緒になることもあるだろ? 目の前を生まれたての子鹿みたいな動き方した後輩がいたら、声も掛けるでしょ」
満面の笑みをたたえたEmmaさんが続ける。
「それにYouranは自転車通学だし、Camilleは車で送り迎えしてもらってるから、メッセンジャーとしてはあたしが適任ってわけ」
「……どういうことですか?」
あたしが聞くと、Emmaさんは、ずいとこちらに顔を寄せて言った。
「今日の放課後また時間くれない? ちょっと相談したいことがあるんだ」
そのブロンドの髪をなびかせて、さも意味ありげに言うのだった。
* * *
そして放課後。
あたしたちは恐らく『バトルをする』と話を聞いたときより、ず~っと大きく口を開けて呆けていた。
「どどどど、どういう意味ですか!?」
「どういう意味も何も、合流しましょうって言ってるの。あなたたちのユニットと、あたしたち3人」
「つまり6人編成でユニットを組まないかってことさ」
え? ユニット? このとんでもなく実力のある3人と、あたしたちが、一緒のチームに……?
「本当ですか!?」
「でも、それで先輩たちはいいんですか? 皆さんに良いことってあるんでしょうか」
あたしと同じようなことを思っていたんだろう、Sophiaが聞くと、3人とも笑顔で答えた。
「あなたたちは友達同士、私たちも仲はいいですしチューター同士ですし。都合がいいと思いませんか?」
「それに楽しそうだしさ。あくまで学内ユニットなわけだから、もし気に入らなかったらすぐ解散もできるしね」
EmmaさんとCamilleさんは優しい声で説明してくれる。
「で、でも、あたしなんか」
「Rinちゃん」
思わず口からこぼれたあたしの言葉に、Youranさんが呟いた。
「あなたと一緒にいることで、私も得られるものがあるかもしれないじゃない?」
「えっ」
その声色はなぜか、少しだけ悲しい色を帯びたようにも聞こえた。
でも、気のせいだったのだろうか、次の瞬間にはYouranさんはいつもの明るい笑顔で、あたしたちにおどけてみせた。
「な~んてね! ほら、3人とも、自信持って! 私たちが自分たちから提案してるんだから。それとも、自分たちだけでやっていきたい? もちろん無理強いはしないよ」
それを聞いたあたしとAmeちゃん、そしてSophiaちゃんはアイコンタクトをして、そして即座に3人とも深く頷いた。
「お願いします。あたしたち、やれるところまでやってみたいです」
「がんばります!」
「お願いします!」
3人で、声を揃えて叫んだ。
「よろっしい! じゃあ今日から私たちは6人ユニットね」
Youranが高らかに宣言すると、自然と拍手が湧き上がった。
「じゃあ、正式に学校側にも登録しに行かないとな」
「チーム名も早々に決めないとね」
「で、でも緊張する……」
「ふふっ、さあ、これから楽しくなるわよ~」
「なあ、せっかくだからこの後ファミレスでパーッとやるか」
「いいですね!」
「ドリンクバー空にするまで飲むぞ」
「あはは、Emmaさんなら本当にやりそう」
「ふふ、じゃあ帰る準備するぞ~!」
あたし、なんだかすごいことに巻き込まれている気がする。
学校に入るときと同じで、やっぱり不安だけど。
でもどうしてこんなにワクワクしているんだろう。
6人の嬌声が、初夏の暖かい空気に溶け込む。
刹那、教室の外に突風が吹き、上空に向けて巻き上がった。