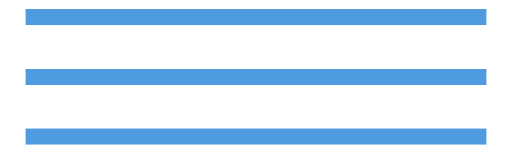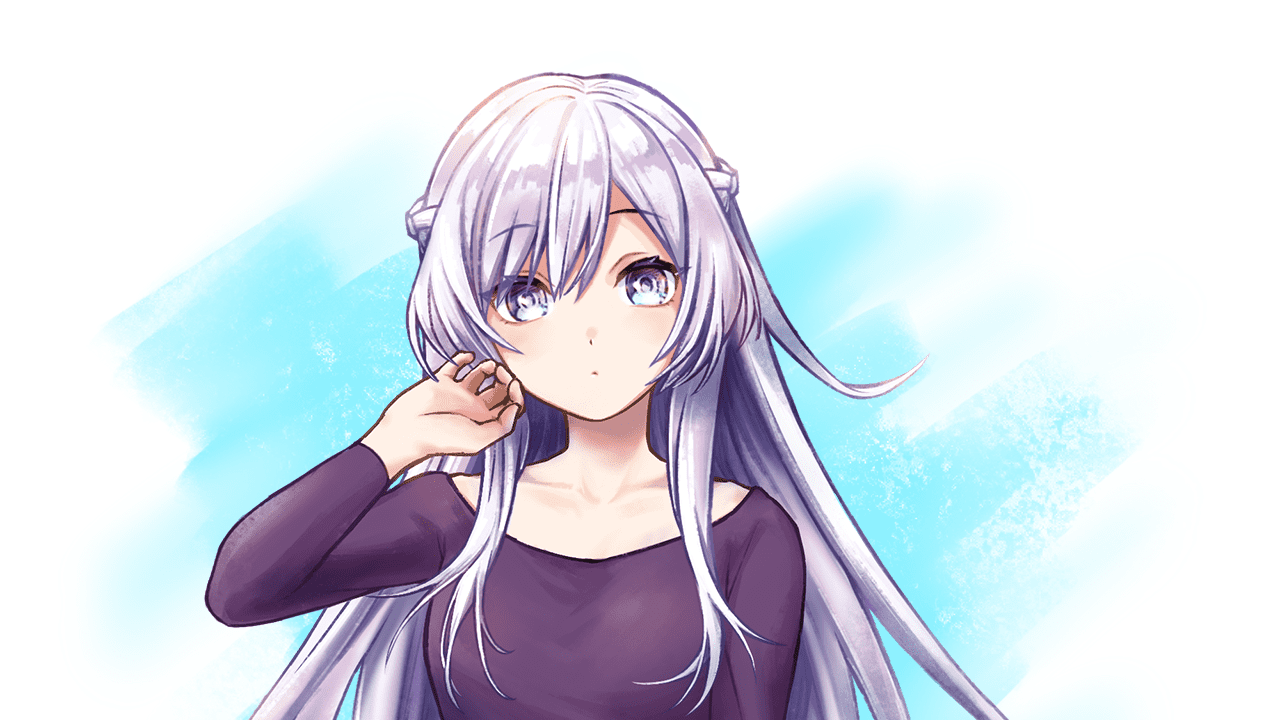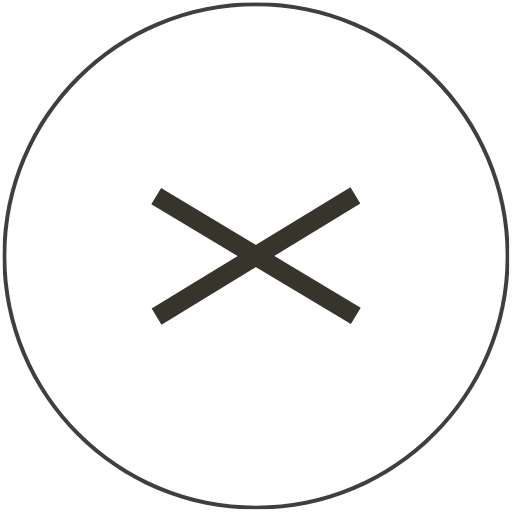晴れた土曜日。RinとAmeliaはハンバーガーショップで遅い昼食を取っていた。
午前中からウィンドウショッピングを楽しんでいた2人は、昼からはSophiaと合流して買い物を続けるつもりだ。
「それにしても……Sophiaちゃんの急な用事って何だったんだろうね」
「わからん。そもそもあいつの考えてること自体よくわからんけどさ」
「あはは、確かに考え方がユニークだもんね」
「まあ、当日の朝にわざわざ電話してくるくらいなんだから、緊急なんでしょ。これ食べ終わる頃には会えるだろうし、あんまり気にしないでいいんじゃない?」
Ameliaはジュースを飲み干すと、椅子から立ち上がり、紙コップを持った。
「お代わりしてくる、確か2杯目ってレシートを持っていくと半額だったよね」
「うん、そうだよ」
Rinの答えに頷いて、Ameliaは1階のカウンターに向かった。
「Sophiaちゃんから連絡は……まだ無いかあ」
窓の外をふと見やるRin。初夏の太陽が眩しく街路樹や歩道を照らしている。
「そろそろ夏だなあ」
「それにしても、Ameliaちゃん、どうしたんだろ?」
ジュースをお代わりするのに5分もかかるだろうかと、Rinが少し心配になってきた頃、ようやくAmeliaが1階から戻ってきた。
「あ、お帰り……って、誰?」
彼女は、その傍らに1人の女性を連れていた。
きれいな顔立ちだが、幼さを残すところからして2人とほぼ同年代だろう、その女性は、にっこりと笑顔でこう言った。
「こんな所で奇遇です、あなたたちがRinさんとAmeliaさんなんですね!」
「……へ?」
それを聞いたRinが呆れた声を同時に出すのには、1秒もかからなかった。
「へえ、Sophiaちゃんの中学からのお友達なんですか」
「ええ、クラスは違ったんですけど、声楽部で同じチームだったんです」
その長身で長髪の美しい女性は、Miaと名乗った。
「ってことはあたしたち同い年ですね」
「そういうことになりますね」
MiaはRinの隣に座り、会話を続ける。共通の話題があったので、3人が打ち解けるのにはそう時間はかからなかった。
「注文カウンターのところで、私に声をかけてきたのは、どうしてなんですか?」
Ameliaが疑問を呈すと、Miaは手に持っていたスマホをいじり、画面を2人に見せた。それは先日3人で撮った写真だった。
「たまにこうやって今でもSophiaが連絡をくれるんです、で2人のことも知ってたんです」
「なるほど、……ちょっと恥ずかしいです」
「だね。……ところで、Sophiaの中学時代ってどんな感じだったんですか?」
AmeliaはさっきからMiaとSophiaの関係に興味津々だ。
「Sophiaの中学時代ですか? うーん……」
スマホを少しいじって、それを机に置くと、しばらく考えてからMiaは答えた。
「初めて会った時は、暗くて誰とも話さない感じでしたね」
その言葉にRinとAmeliaは疑問符を浮かべる。今のSophiaからはあまり考えられない様子だったからだ。
「Sophiaは声楽に関してはトップクラスの実力ですけど、それって中学に入った時から既にそうだったんです」
「あ、やっぱりそうなんですね」
「で、私たちの中学って声楽部が有名だったので、それが理由で転校してきたみたいで、2年の初めの頃から入ってきたんですね」
2人はSophiaの頃に転校を経験していたとは知らず、うんうんと深く頷きながら聞いている。
「そういうわけだから、声楽部にも当然入ってきたんですけど、誰とも話さないっていうか、コミュニケーションを取らない子だったんですね。で、みんなも距離を置こうとするから」
「それじゃあ、完全に浮いちゃってたんじゃ」
「ええ、もうそれは完全に」
Miaはふふっと微笑みながら続ける。
「でも、本人はコミュニケーションを取りたくないんじゃなくて、取り方が分からないだけだったみたいなんです」
* * *
2年前のある朝、Sophiaは朝練習をするために屋上で準備体操をしていた。
「おはよう」
そんな彼女に、たまたま個人練習をスタートさせようと、同じように早朝学校に来たMiaが声をかけた。
「あ、お、おは、よう……」
Sophiaは最初、おぼつかない挨拶をするだけだった。
きっかけは本当に何となくだった。
最初はお互いに挨拶するだけだったが、結局狭い空間で声を出さないといけないので、お互い声を掛け合うようになり、しばらくすると挨拶だけでなく、アドバイスや雑談もするようになった。
「私、将来バイオリンを作る人になりたくて。留学しようと思ってるんです」
「すごいね」
「Sophiaは?」
「えっと、私は、声楽を続けたい。あと……」
「あと?」
「……友達がほしい。やっぱり、一人は、寂しいかな」
その後2人はどんどん仲良くなり、声楽部のMiaの友人たちと合流して、声楽コンクールを目指すことになった。
Sophiaはどんどん頭角を表し、その実力でぐいぐいとチームのレベルを上げ、ただし決して上から目線ではなく、メンバー分け隔てなく全員に献身的に尽くした。
メンバーとの相性が良かったのもあったのだろう、全員がSophiaを心から受け容れた。
周囲には、彼女は実力的にソロでも十分だという意見も多かった。
ただし、Sophiaは断固としてグループセッションにこだわり、ソロとしてはコンクールにエントリーさえしなかった。他のメンバーが足を引っ張っているのではという揶揄には激昂し、メンバーが逆にそれをなだめることさえあった。
そして3年春の声楽コンクール。チームは見事地方大会を金賞で突破、全国大会も入賞を果たした。
学校に錦の旗を持ち帰ることに成功し、お互いを称え合うメンバーの中、ぼそっとSophiaはつぶやいた。
「……みんなで歌うのって、楽しいよね」
それを聞いて、MiaたちメンバーはSophiaを抱きしめ、感激の涙を流した。
* * *
「Sophiaは誰かと一緒に何かを作り上げることがとにかく好きで、自分が持つ声楽家としての能力は、そのための手段だって捉えてる気がするんです。それくらい本当は人懐っこい子なんです」
Miaの意見に、2人も深く感心する。
「今の学校にも、もちろん声楽家としてプロになりたいのはあるんだろうけど、そういう仲間を探しに入ったのもあるのかなって。だからせっかく出会えた2人にも誤解して欲しくないなあって思うんです」
「はい、大丈夫です。あたしも、アイドルになりたくて、一緒の方に歩いていられるの、楽しいですから」
「変わったやつだけど、悪いやつじゃあないですね」
RinとAmeliaは当然と言わんばかりに即答した。
「そう思ってくれてるなら、よかったです」
笑顔でMiaもそれに応えた。
「私は今、楽器製作の勉強で手一杯なので、Sophiaのこと、よろしくお願いしますね」
「あ、はい。というか、あたしの方がSophiaちゃんに頼りっぱなしですけど……」
「あはは、それもそうだ」
「え~、Ameちゃんひどい~」
3人は声を上げて笑った。
「でもさ、こんな話聞いちゃって、Sophiaちゃん怒らないかな……」
「まあ、昔の話だもんな」
一瞬神妙な顔つきになる2人。それにMiaは笑顔を崩さず即答した。
「え? さすがに私も了解を取らないで、昔の話なんてしませんよ」
「……え?」
「もう随分前にSophiaにメッセージを送りましたよ。あなたの親友の2人と会って、昔の話をしてるって」
「……で、何て返ってきたんですか」
「『今すぐそこに行くから待ってろ』って。20分くらい前ですかね」
Miaの言葉に2人は凍る。
「え……それって……」
「『了解を取った』とは言わないんじゃ……」
窓の外をふと見やるRin。引き続き初夏の太陽が眩しく街路樹や歩道を照らしている。
――その中、何者かが猛ダッシュでこちらに近づいているのが見えた。
「あ、あれ……」
「……間違いない」
2人はほぼ同時にごくりと息を飲んだ。
「あら、今日も元気ね、Sophiaは。ところで、ここはお代わり、半額でできましたよね?」
そんな2人を見ながら、呑気に立ち上がるMiaだった。
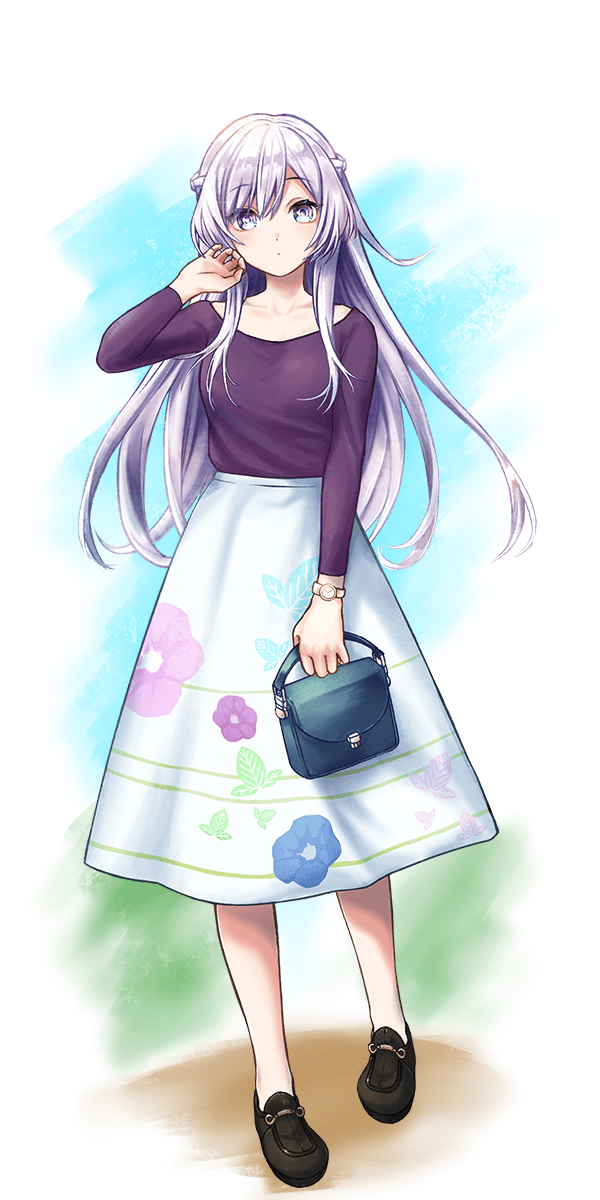
イラスト:桜祐